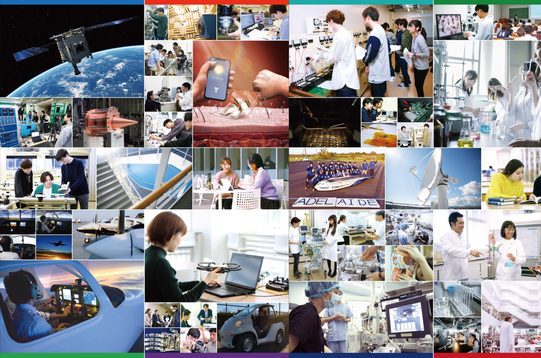湘南キャンパスで8月5日に、秦野市・伊勢原市と本学の関係者による「災害救助に活用するドローンに関する意見交換」を開催しました。当日は、秦野市・伊勢原市共同消防指令センターと両市危機管理部門の担当者ら14名が来訪。本学から工学部の山本佳男学部長、医学部の中川儀英教授(医学部付属八王子病院副院長)、情報理工学部の内田理教授(情報技術センター所長)が出席しました。
冒頭で山本学部長が、本学の沿革や各キャンパス・学部の概要などを説明。2日と3日に開催されたオープンキャンパスで建築都市学部土木工学科と工学部機械システム工学科の「コラボ企画」としてドローンの防災面への活用について紹介した際の様子をはじめ、大規模自然災害発生直後の人命救助のリミットとされる「72時間の壁」に対して昼夜を問わず使える3次元レーザースキャンやサーマルカメラを搭載したドローンを使った人命救助や捜索の可能性について解説しました。
次に中川教授が「災害医療と課題」と題して、阪神淡路大震災以降に進んだ災害医療体制について解説。災害拠点病院の整備やドクターヘリ導入が進んだ経緯について話し、日中に限られることが多い探索救助活動の限界や、能登半島地震における被災状況に関する情報収集といった災害医療が抱える課題を提示しました。続いて内田教授が、「災害時のソーシャルメディア利活用」をテーマに登壇。災害時はリアルタイムな情報と正確な情報の両方を収集する必要があるとして、市職員や消防団員、自治体役員やボランティアなどで構成する「市民情報団」(仮称)による災害時の情報収集・発信のSNS活用の仕組みについて提案しました。
その後、芝生広場「Palletパレット」に移動し、ドローンと4足歩行ロボットのデモンストレーションを実施。参加者はドローンが飛行する様子を観察し、4足歩行ロボットのリモコン操作などを体験しました。会議室に戻って行った質疑応答では、登山者による事故が多いといった秦野・伊勢原管内の特徴や、頻発する土砂災害で捜索時の労力を軽減するパワースーツ活用の可能性、山岳遭難多発地点の地形を3D化する技術や経験の浅い救助隊員に対する教育訓練時へのIT活用などについて、活発に意見が交わされました。山本学部長は、「防災では地域連携が非常に重要になります。今後もこのような最新の研究成果と災害救助現場の情報交換の場を設けていきたい」と話しました。