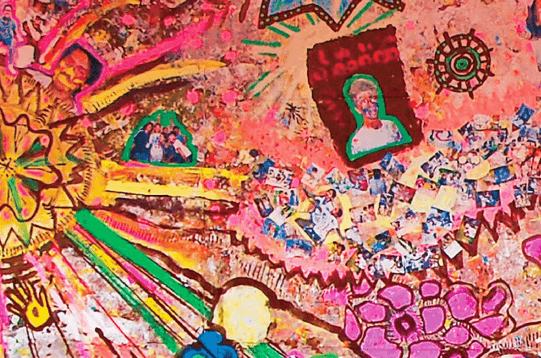国際学部のプロジェクト型科目「Global Action Advanced B」を履修する学生たちが、8月10日に横浜市・泰生ポーチFRONTでミニ講座「紛争避難者、迫害対象者《難民》の現実」を開催しました。授業を担当する木下理仁非常勤講師が事務局を務め、開発教育と国際理解教育を推進するNGO「かながわ開発教育センター(K-DEC)」が運営する「K-DECカフェ」の一環として開催されました。
当日は、授業内で難民に関して学んでいるグループの土門弘二さん(国際学部4年次生)と緑川詩乃さん(同3年次生)が「ミニ講座 難民問題の基礎知識」と題して、日本における難民認定数の推移など難民問題の基礎知識を紹介し、ウクライナ避難民の受け入れにより、低い難民認定数を補う補完的保護制度の必要性が示されたと説明し、「今後は制度の柔軟性や透明性を高め、国際基準に沿った人道支援を拡充していくことが課題です」とまとめました。



続いて、ルワンダ共和国から来日中のガテラ・ルダシングワ・エマニュエル氏とルダシングワ(吉田)真美夫妻が、「ルワンダの虐殺、私がみたもの」をテーマに登壇。木下講師がインタビュアーを務め、現在は真美さんとともに義足を作っているガテラさんの幼少期の記憶や、民族対立による混乱を避けて隣国ケニアに逃れた際の様子、 祖国に戻って経験した命の危険を感じるほどの迫害などについて、当時の思いを語りました。
次に、神保優貴さん(国際学部4年次生)と下山真弘さん(同)が鎌倉市にあるNPO法人「アルペなんみんセンター」を訪問した際の様子を紹介。現地で会った元パイロットの難民と話した経験を振り返り、「過去について話すこと自体が辛そうだと感じました。難民として日本に来るまでに想像を絶する困難かつ過酷な状況があったと実感し、今後も難民問題に理解を深めていきたいと思いました」と話しました。



最後に、加藤雄也さん(同)、森七海さん(同3年次生)、堀江傑さん(政治経済学部3年次生)が司会進行を務め、ロシアによる軍事侵攻から逃れて日本に来たウクライナ避難民2名による講演「ウクライナから日本に来て」を実施。北西部リウネ出身のカテリーナさんと首都キーウ出身のリリアさんが登壇し、日本で母国の支援活動に関わり、地域住民と交流する中で感じたことや、ウクライナに残る家族や親族、一時帰国した際の状況などについて解説し、「自分たちの言語で話し、文化を大事にできる公平な平和がほしい」と話しました。



各プログラムの間には参加者同士がテーブルごとに、「開けたコミュニティのあり方」「日本語教育を含む日本ならではの支援」「今後の難民受け入れの考え方」などをめぐって討論し、日本における難民支援の課題などについて理解を深めました。木下講師は、「こうした機会に難民の方々の“生の声”を聴いて、難民問題は遠く離れた場所のことではなく、自分たちと同じように考え感じて生きている人たちの問題であると実感してほしい。学生たちには、このようなイベントを通して自分たちが調べ、考え、感じたことをどのように多くの人に伝えるのか伝えるのかを学んでほしいと思います」と話しました。