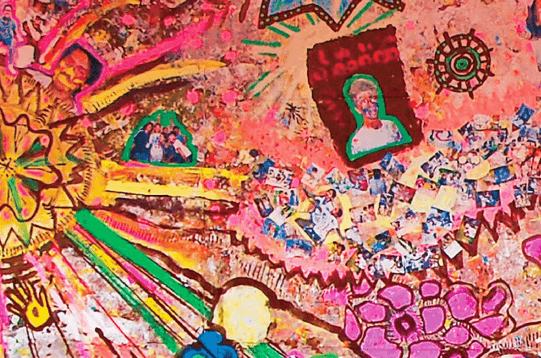国際学部のサマーセッション科目「Global Study Tour A」を受講する学生15名が8月5日から7日まで、指導教員の荒木圭子教授(学部長)と共に被爆80周年を迎えた広島市を訪問し、平和記念式典やさまざまな関連事業に参加しました。国際社会で責任ある行動のできる人材育成を目指す本学部では、平和の構築・維持を中心的なテーマのひとつとして捉えています。今回の研修は、荒木教授がさまざまなプロジェクトを介して横浜市在住で95歳の被爆者・齋藤孝さんと出会い、実現したものです。


学生たちは5月25日に齋藤さんと面談。齋藤さんが15歳の時に広島にて被爆して九死に一生を得た後に原爆症に認定され、闘病する一方、「みなとみらい21」のオープニングイベントをはじめ地域づくりに貢献を続けてきた歩みや、非核化への思いなどを聞きました。その折に、齋藤さんからさまざまな方との交流を通して集めた折り鶴を奉納するために千羽鶴にしてほしいと託され、8月6日に齋藤さんと一緒に広島を訪問し、平和記念公園に奉納する約束を交わしました。学生たちは齋藤さんとともに平和記念式典に参列し、平和記念公園で合計1万羽以上にもなる千羽鶴を奉納しました。



学生たちはまた、6日の午後に旧日本銀行広島支店ビルで行われたイベント「平和と美術と音楽と」に参加。マキ・ワーティック・イーサ・ヤスミンさん(国際学部4年次生)は、会話劇「国境を越えたひとつの家族~平和のための対話~」に長女役として出演しました。スーダン出身のヤスミンさんは、歴史的に内戦や紛争を経験してきた母国に思いを馳せ、「世界がひとつの家族だという考え方に触れ、紛争解決や戦争反対を訴えるための手段はデモやボイコットだけではないと感じました。私にとっての平和とは、安心して暮らせる状態を一人ひとりが思いやりをもって作ることです。批判し合うのではなく、“皆が家族”と思い互いに接すれば、相手も変わるかもしれないと思います」と話しました。

7日には近隣の公民館で今回の訪問を振り返る授業を実施。学生からは、「広島に来て、齋藤さんが話していた“核兵器をなくしたい”という言葉の重みを実感した」「多くの人が世界中から平和を願い広島を訪れる様子を目の当たりにして被爆国の人間として平和を訴え続けることが大切だと改めて思った」「広島の街や人から明るく前向きなエネルギーを感じ、生き抜いてきた強さを感じた」「資料館の遺品に一人ひとり持ち主がいたと考え、平和という言葉の重さを知った」など多くの感想や意見がありました。
荒木教授は、「今回の研修は、齋藤さんとのつながりを大切にしながら、広島を観光客のように訪れるのではなく8月6日に、平和活動の一端に参加することで、平和について体験的に学ぶ機会になりました。学生たちは8月6日の広島に集まった多様な人たちを見て、“平和とは何か”の定義が人や国によって異なるのではないかと気づき、平和を目指す方法も異なり、その違いによって対立が生まれていることも知りました。卒業後はそれぞれの立場や方法で平和を考えていくことになると思いますが、彼らが社会に散らばっている市民同士の一員として網目のようにしっかりつながっていくことで平和が盤石なものになっていくのではないかと考えます」と話しました。