東海大学海洋研究所の原田靖特別研究員が9月20日に、静岡県地震防災センターで開催された「ふじのくに防災学講座」で講演しました。静岡県では、県内の国公私立大学と県教育委員会、静岡地方気象台、報道機関などによる「しずおか防災コンソーシアム」を形成しており、本講座はその啓発活動の一環として県内各地で定期的に行われています。
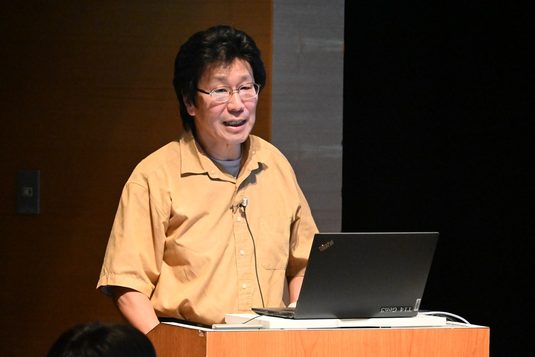
原田特別研究員は「想定される南海トラフ地震の津波シミュレーション」をテーマに登壇しました。まず地震が起こる仕組みについて、プレート境界や断層運動を示しながら解説し、「現在静岡県では、南海トラフ地震の被害想定を1703年に発生した元禄型関東地震の浸水域と重ね合わせて計算し、“浸水マップ”を公開しています。私はこのデータに、第1波や第2波などの時間変動を加味するため、津波シミュレーションソフトウェア“JAGURS”を用いて独自のシミュレーションを行っています」と紹介しました。さらに、南海トラフ地震が発生した際の浸水域を時間ごとに示したシミュレーション映像を提示し、東日本大震災との違いについて「震源距離が近いため、津波到達時間が短いことが特徴です。揺れも強く、内閣府は死者数を最大で32万3000人、焼失棟数を最大で238万6000棟と想定しています」と説明しました。最後に「シミュレーションでは現状、建物が津波で破壊される計算はできません。また、想定される深層断層モデルと同じ地震が発生するとも限りません。想定外の事象が起こり得るため、できる対策を確実に進めることが大切です」とまとめました。







