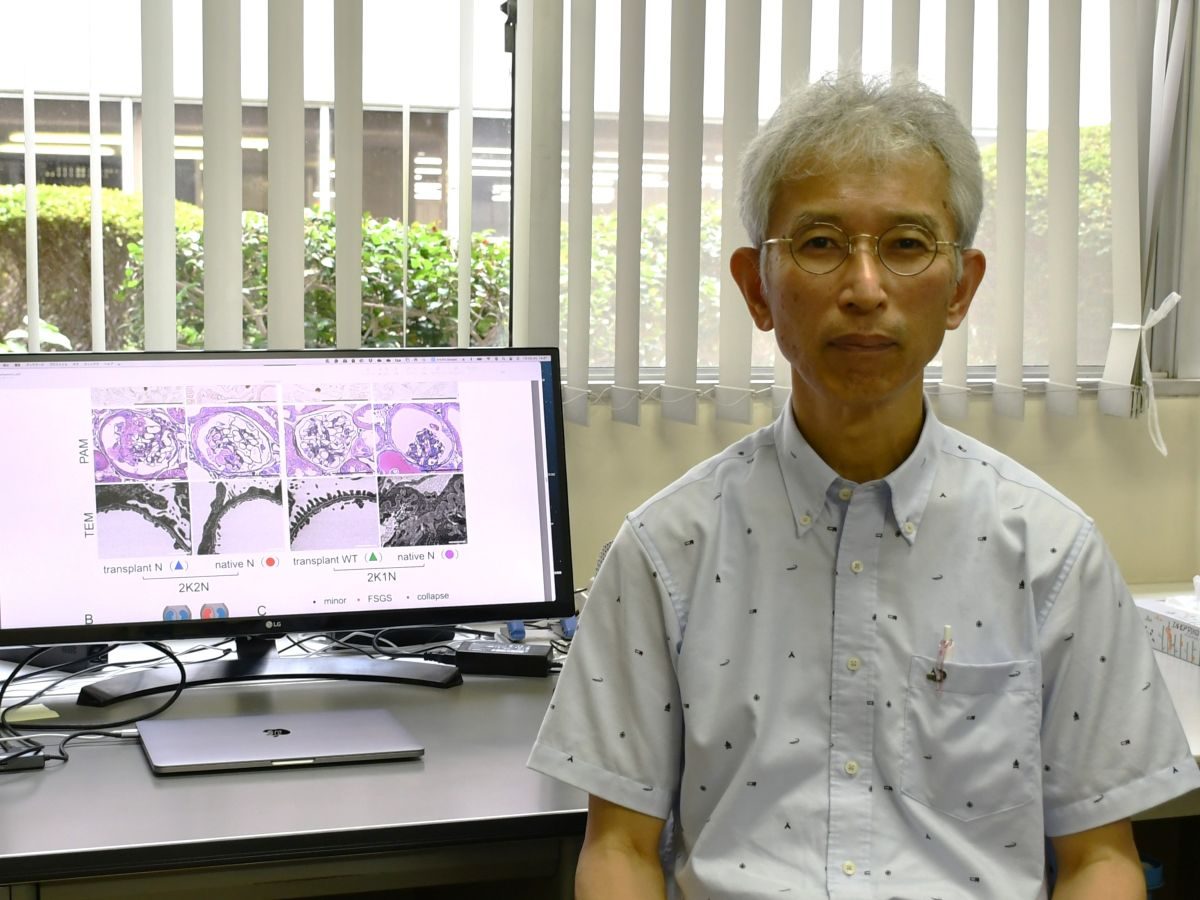
医学部医学科基礎医学系生体機能学領域の松阪泰二教授(総合医学研究所)らの研究グループがこのほど、左右の腎臓が互いの機能のバランスを調節するメカニズムを解明。その成果をまとめた論文が6月20日に、日本学士院が発行する英文学術誌『Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, Physical and Biological Sciences』オンライン版に掲載されました。
腎臓は腹部の左右に一対あり、血液中の老廃物や塩分をろ過して尿として排出するほか、体内の水分量や電解質の濃度、血圧を一定に保つといった体のバランスを調整する役割を担っています。多くの腎臓病では両方の腎臓が等しく障害されますが、何らかの原因で一方の腎機能が低下した場合、もう一方の働きが高まる「腎カウンターバランス」と呼ばれる現象が知られていました。しかしそのメカニズムは明らかになっていませんでした。
松阪教授と筑波大学医学医療系の大学院生・坂本和雄さん(現・神戸大学医学部附属病院特定助教)、 同・川西邦夫助教(現・昭和医科大学医学部)らは、 片側の腎臓の糸球体足細胞(老廃物をろ過する糸球体の上皮細胞=ポドサイト)に障害を与えて機能を失わせたマウス(2K1Nモデル)と、両側の腎臓に障害を与えたマウス(2K2Nモデル)を作製して比較。その結果、2K2Nモデルでは通常の腎臓病のように蛋白尿や全身性の浮腫が出現したのに対し、2K1Nモデルは障害腎の血流が低下・途絶し、糸球体虚脱(潰れる現象)という特異な形態を示していました。 さらに、2K1N モデルでは血圧の上昇や血管収縮に関与するホルモン「アンジオテンシンII 」(Ang II)が障害腎のみで過剰に産生され、このAng IIの局所的不均衡が血流低下と糸球体の虚脱を引き起こすことを明らかにしました。
腎臓内科の医師でもある松阪教授は、長年にわたりポドサイトに注目して基礎研究を続けており、本研究の基盤となるポドサイトの機能を失わせた遺伝子改変マウスを作製。ポドサイトの障害によりAng IIが多く産生されることも発見しており、「Ang II は血圧等によって調節されますが、今回の研究によってポドサイト障害が局所的にAng II を増加させるという仮説を裏付けるデータが得られました」と成果を説明します。増加したAng IIは、腎臓病にみられるむくみを起こし、また腎臓の障害をさらに増悪させる可能性があります。「高血圧や糖尿病、糸球体腎炎などにより発症する慢性腎臓病(CKD)は進行すると透析や腎移植が必要になるなど世界的に問題となっており、日本では20歳以上の7~8人に1人がCKDに罹患しているとの報告もあります。治療法を開発するためには基礎研究の積み重ねが不可欠であり、さらに研究を深めたい」と今後への意欲を語っています。
※『Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, Physical and Biological Sciences』に掲載された論文は下記URLからご覧いただけます。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjab/advpub/0/advpub_pjab.101.025/_article



