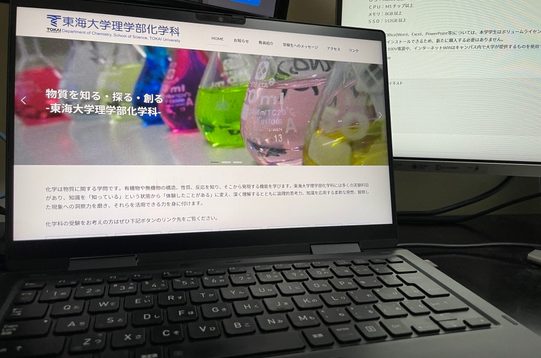A.薬の成分が血液に乗って患部に運ばれ、体内の反応を促したり、抑えたりするからです
理学部化学科・岩岡道夫先生(先進生命科学研究所所長)

薬は体の中に入ったあと、血液を通じて全身に運ばれ、細胞の表面にある受容体や細胞内の酵素と結合することで薬効を示します。例えば、痛みや熱などの炎症反応の原因となる伝達物質の代わりに薬の分子が受容体と結合することで、特定の反応が促されたり、反応が抑えられたりすることで病気の症状が和らぎます。
風邪や熱を出したときには、生姜やネギが効くという民間療法を聞いたことがあるかもしれません。これは、先人の経験則から受け継がれてきた対処法で、「絶対に効く」という保障はありません。初期の薬も同じで、柳の皮から生まれた頭痛薬「アスピリン」やアオカビから作られた「ペニシリン」は、効果を発揮する仕組みがわからないまま、「症状が和らぐ」という経験則に基づいて使用されてきたのです。
とはいえ、時代を経るごとに科学は進歩するもの。最近では薬の成分がどの受容体や酵素に結合するのかがわかるようになり、病気の原因を直接狙い撃ちし、効果を発揮する「分子標的薬」が開発されるようになっています。ただ一方でこの薬は標的から外れることがあり、効果も長続きしにくいという欠点もあります。そこで新たに30年ほど前から研究されているのが、「共有結合阻害剤」です。標的を狙い撃つだけでなく「共有結合」という強い化学結合を作って標的と結びつき、薬の効果を長く保つのが特徴です。
このような薬の多くには「硫黄」が含まれており、薬効の発現に重要な働きをしています。私の研究室では「硫黄」と化学的性質が似ている「セレン」という元素に着目し、病気の原因となる酵素の働きを抑える新しい化合物を生み出す研究を行ってきました。最近では、細胞内の重要な還元物質である「グルタチオン」と呼ばれる小さなペプチドに含まれる「硫黄」を「セレン」に置き換えた「セレノグルタチオン」の合成にも成功。これが「硫黄」のときよりも1000倍近い薬理作用を示す抗酸化剤となる可能性を見出しました。この化合物の特性をさらに高めることで、「セレン」を使用した世界初の新薬を生み出すべく日々研究を重ねています。
化学の研究では、新たな化合物を生み出すのに試行錯誤が欠かせません。何十回も失敗することもありますが、諦めずに続けて成功したときの達成感は格別です。フラスコに材料と触媒を入れて、火加減や攪拌方法を調整しながら新物質を作り出す「ものづくり」の楽しさ、ばらばらの情報を組み合わせて物質の性質や構造を読み解いていく「謎解き」の興味は、飽きることがありません。そんな「面白い」を追求したい人にとって化学はぴったりの分野です。新しい化合物を生み出し、性質を探っていく研究の旅を一緒に歩みましょう。
いわおか・みちお 博士(理学)。東京大学教養学部助手、東京大学大学院・総合文化研究科助手を経て、2003年東海大学理学部化学科に着任。2022年から先進生命研究所所長を兼務。専門は、たんぱく質化学、有機化学