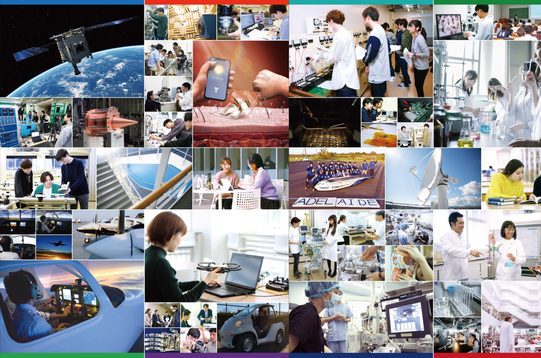資格教育センターの篠原聰准教授と学芸員の資格取得を目指す学生たちが9月25日と10月23日に、神奈川県立平塚盲学校で同校の児童・生徒を対象に造形ワークショップを実施しました。2021年度まで3年にわたり神奈川県と本学が展開してきた「ともいきアートサポート事業」の主旨を受け継ぎ、新たに「地域連携によるユニバーサル・ミュージアム普及事業」として同校と本学が2023年度から取り組んでいるものです。

ワークショップでは筑波大学芸術系准教授の宮坂慎司氏が講師を務め、表面に突起がついた棒状の鋼材(鉄筋)や紙粘土、木造彫刻の制作過程で廃材となる木っ端などを材料に使用。宮坂氏は、藤沢市で活動する彫刻家の桒山賀行氏から提供されたクスノキの丸太を削り、「削りたての木はとてもいい匂いがします。彫刻の作業現場では木を削る音や匂いによって作品の“気配”を感じることがありますが、皆さんも日ごろそういった経験はありますか? 好きな場所や物、匂い、音などを思い浮かべながら完成を目指してください」と語りかけました。児童・生徒たちは、好きなキャラクターや遊具、動物、乗り物など、さまざまなテーマで作品づくりに挑戦。空間を大きく取ったり情景を考えたりとイメージを膨らませ、学生や教員がサポートしながら完成した作品について一人ひとりタイトルとポイントを発表し、宮坂氏が形状や使用した材料などを説明しました。参加した生徒は、「こんなにたくさんの粘土や木片に触れる機会はないので、一から作品を作り上げるのはとても大変でしたが、大学生や先生たちと一緒に作るのはすごく楽しかった。触感や匂いなど、いろんな楽しみ方がありました」と話していました。

佐久間祐樹さん(文学部4年次生)は、「同じ材料を使っているのに一人ひとり全く違う作品が出来上がり、発想力の豊かさに驚きました。普段から触覚や嗅覚を頼りに物体の情報を得ることが多いからこそ培われるのだと思います。大学に入学する前は“芸術作品は触らずに鑑賞するもの”という考えでしたが、篠原先生の授業を通じて、視覚情報だけでなく“作品を触って楽しむ”方法があることを学んできました。こうしたワークショップを通じて子どもたちが芸術作品をより身近に感じ、楽しんでもらえるようになるとうれしい」と話していました。
なお、完成した作品の展示会を来年開催する予定です。
※本活動は、JSPS科研費JP25K00422の助成を受けた研究・取組および筑波大学芸術系と共英製鋼株式会社による共同研究「アートの視点によるサスティナブルな建築鋼材の可能性開拓」の協力を得て実施しました。