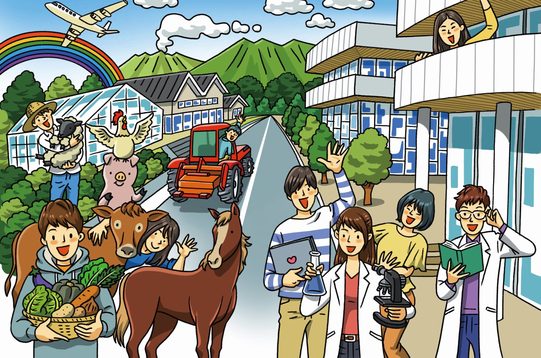9月に熊本キャンパスの農学部の学生が、総合農学実習で沖縄地域研究センターを訪れカリキュラムの一部を行いました。今回は、実習を行った学生の声を一部抜粋して紹介します。

・今回の実習を通してトレッキングの大切さや楽しさを知ることができました。西表島では海と山に行ったのですが、ガイドさんが楽しくわかりやすく説明してくれるおかげで早く知識を吸収することができました。また、カンビレーの滝に向かう最中、木に手のひらサイズの水の入った穴があったのですが、その中で食物連鎖が起こっていると聞いたときは考えもしてなかったので驚きました。事前に知識や人伝で聞いたこととは全く違うのでいってよかったと思うことができました。
・西表島で特に驚いたのは生態系です。私は埼玉出身でカモシカや県民の鳥であるシラコバトなどがいますが、緑の面積は3分の1ほどで生物の生息数が減少しています。他の県でも同じようなことが言えることができ、私自身旅が好きでさまざまな地域に行きそこの歴史・文化や自然を見て学ぶなかで昔と比べ環境と比例するように徐々に希少生物や天然記念物が少なくなっているなと感じていました。西表島では、イリオモテヤマネコやセマルハコガメなど希少な生物を保護するため徹底した調査や生息環境の保全・再生を行っていることを知るたびに驚嘆しました。また、野良猫を保護・譲渡して数を0にし、イリオモテヤマネコの生息を保つ行いには尊敬の念しかありませんでした。西表には3日しかいませんでしたが、さまざまな生物や伝統行事であるアンガマを見ることができました。ですが、まだまだ知らないことが多いため、より多くの知識を身につけ再び西表島に行ってみたいです。
・西表島で浦内川の下流から上流のカンビレーの滝までトレッキングをしました。下流にはマングローブが広がり、歩き始めると温帯地域では見られない植物や、西表島だけに生息する動物も見られました。トレッキング後はマングローブで、そこに生息する動物の特徴やそれらを取り巻く生態系のことなどを学びました。また、星砂の海岸では星砂はもちろんのこと隆起した地層やそこから発見出来る化石についてなどその仕組みそのものを学ばせて頂きました。これらの経験を通して、いかに学習においてフィールドの経験が必要なのかということを実感しました。実際に自分の五感で生物やそれらを取り巻く環境に触れるということが大事であり、座学だけはなくそれを絡めてより理解を深めること、刺激を得るにはフィールド学習が一番でありそれを得られた実習であったと思います。西表島には陸・海・空と離島の独自の生態系やその形成過程である過去からの流れを知り得る情報が至る所に膨大に溢れており、その環境の中に沖縄地域研究センターがあるというとても恵まれた環境で学習できたことに感謝です。
・西表島の野生生物保護センターでは、イリオモテヤマネコの生態を学び、なぜ西表島という厳しい環境で生き残って来られたのか、国の天然記念物になったのかが理解できた。船浮でのじゃじゃまるツアーでは、普段見ることできない海の中を見られて海の中はこんなに綺麗だと感じた。また、船浮に泊まったとき、朝から船を出してウミガメを見せてくれるなど沖縄の人の暖かさ、面倒見の良さを感じた。西表島でのトレッキングでは、自分は山登りが好きでよく山登りをしていたため、本島で見たことのある植物もいれば、西表島ならではの植物があるなど、亜熱帯と温帯での自然の共通点・相違点を見つけることができる貴重な体験ができた。また宿に泊まった際に拝見した旧盆の祭りは、踊りと音で先祖の霊を呼び戻していて、長崎の精霊流しと似ていて、どこか懐かしさを感じる新鮮な祭りでした。
・西表島での実習を通して、新しい発見に繋がる様々な経験を得ることができた。
浦内川トレッキングで観察できた木のくぼみにある食物連鎖や、地元ではあまりみない明るい色の生物には驚かされた。これらの生態系は、独自の微生物群集や植物との共生関係などから、食品の機能性向上や新しい食品素材の開発に繋がる可能性があると感じた。
また、マングローブ林で観察できたハクセンシオマネキが印象に残った。地元の干潟でもよく観察できる生物の亜種が自然環境の異なる西表島にいることに驚いた。どのような経緯で西表島にやってきたのか、形態的・生理的な違いがあるのかといった疑問などに興味をもった。西表島の生態系から得られた知見を活かし、さらに学びを深めていきたいと感じた。
・今回の西表島の実習では船浮湾とテドウ山近くのトレッキング研修、マングローブ林、星砂海岸の実習など、どれも決して自分だけでは体験することが出来なかった経験をして新しい学びを沢山得た。特にトレッキングでは、自分の地元では見られないような植物の形態や昆虫を観察することが出来て新しい体験で、とても面白かった。植物などの観察では、その土地に適応するための形がとても分かりやすく疲れを忘れて歩いていた。午後のシュノーケリングでは、色鮮やかなサンゴや海洋生物の観察をした。そして昔は人が生活を送っていた跡地などの観察を行い、昔の人の行動や家の材質や庭からどんな生活をしているのか感じることが出来とても不思議な気持ちになった。
・今回浦内川の遊歩道でのトレッキングでは自分の考えが覆るような経験をさせていただき感動や驚きがいくつもありました。西表島の植生はこうだろうという想像を超えてくる種類、西表の環境だからこそできる生態系を目視できたことは貴重な体験だと思いました。また展望台から臨むマリユドゥの滝やカンビレーの滝はスケールの大きさや見入ってしまうような圧巻さから多くの時間感動していました。亜熱帯と温帯での環境や生態系の違いなどは知っているつもりでしたがまだまだ自分の知らない事ばかりだと知る機会となりました。トレッキング中で出会った見たこともない色をした生物や昆虫なども調べなければわからないものばかりでした。その土地の環境を知ることの中で実際に自分の目で確かめることができたことは大きな財産になったと思いました。
・西表島での滞在は3日間で亜熱帯の海中から山中まで観察しましたが、正直3日間では時間が少なく感じました。再度訪れる際は1週間滞在して観察したいと思えるほどに観察対象が多く、潮間帯や沿海域の観察は実習の期間が大潮であったのもあり潮の満ち引きで大きく姿が変わりました。潮間帯ではマングローブやミナミコメツキガニを代表とした生物を観察できました。また、崎山湾・網取湾での水中観察ではサンゴ礁の白化の現状と回復の希望となる動きの説明を聞きながら見られた貴重な体験をすることができました。網取施設では集落跡の木々の生え方に自然の強さと自然に対して本来人は弱い物だと感じさせられました。最後に現地の紫外線はとても強く、普段から素肌が出ていた箇所はそれほどでしたが、それ以外の箇所は滅茶苦茶なくらいに焼けていました。ですが、それもある種、貴重な体験になりました。
・今回の実習では、これまで見ることのできなかった景色を見られたり、やったことないことを体験できたりして楽しかったです。八重山でのフィールドワークでは仲間と一緒に山を登るときに、それぞれが見たいものを探していて、これまで私が気にしていなかったものを見ることができ、新たな視点を知ることができました。
普段は見ることのできない本州や九州とはまた違った特徴を持つ亜熱帯地域特有の植物を見ることで、環境が植物に与える影響の大きさを知ることができました。
・今回参加させていただいた西表島での実習は、豊かな自然がもたらす生物多様性の素晴らしさを肌で感じる貴重な体験でした。マングローブ林が持つ独特な生態系を目の当たりにし、座学で学んだ知識がリアルなものとして結びつきました。この実習ではヤエヤマヒルギ・メヒルギ・オヒルギの3種類のマングローブを観察でき、支柱根・板根・膝根それぞれの違いがよく分かりました。また、テレビでしか見た事のなかったシオマネキの威嚇を実際に見ることができ、実際に来ることで感じられる西表島の素晴らしさを体感することが出来ました。この実習で得た経験と感動を、今後の学びや研究に活かしていきたいです。