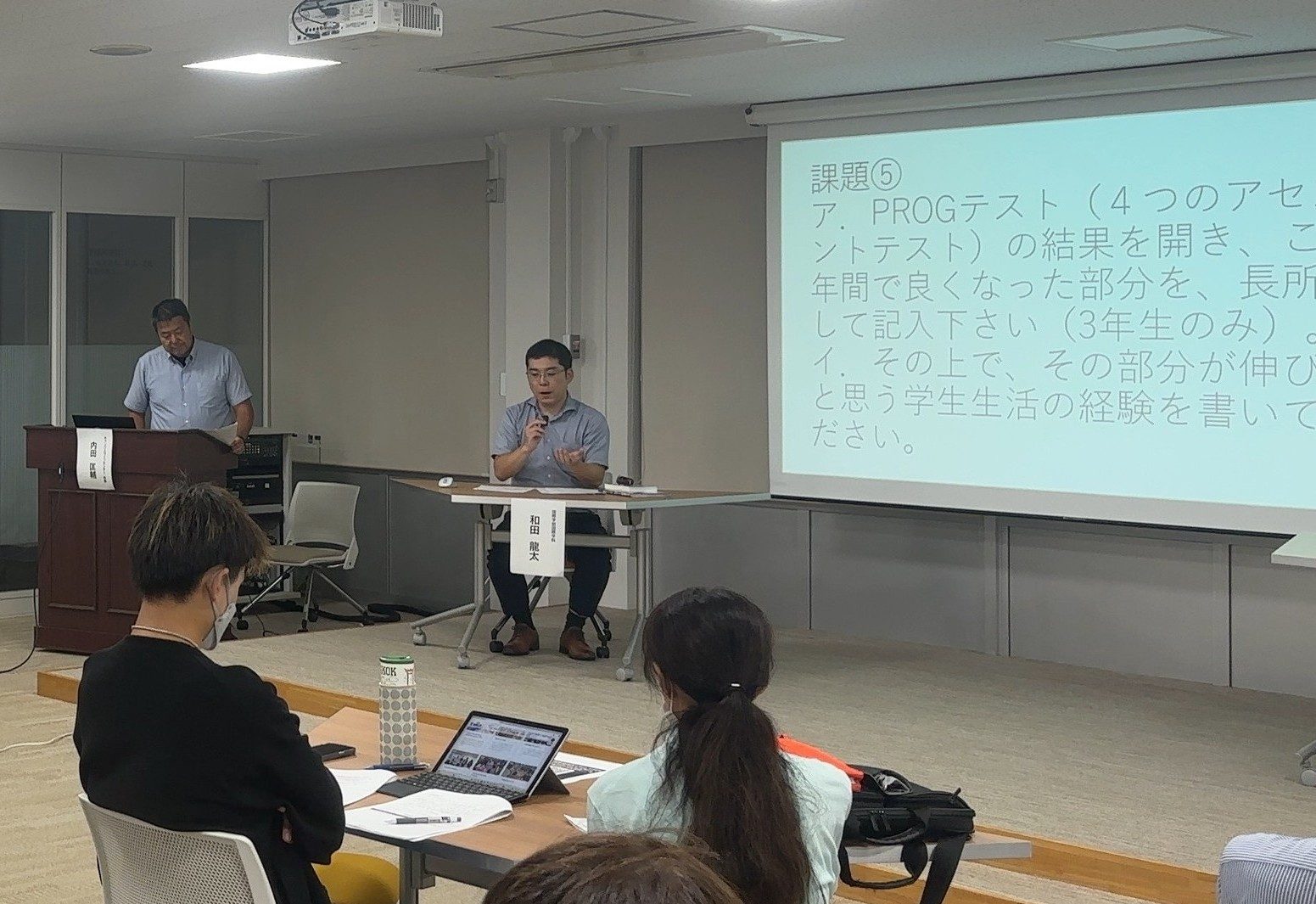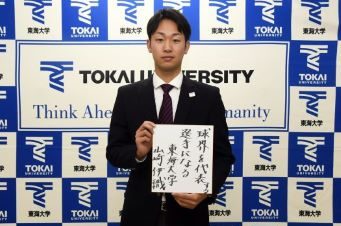東海大学では、2025年9月18日(木)にFD・SD研修会「PROGテストをどのように活用する?~学生の成長を促す活用事例~」を対面およびオンラインのハイブリッド形式で開催し、約80名の教職員・学生が参加しました。
本学では1年次と3年次を対象に、学生の汎用的な能力・態度・指向性を測定する「PROGテスト(Progress Report on Generic Skills)」を実施しています。本研修会は、その結果を組織として活用する他大学の事例や学生の成長を促す取り組みとして授業で活用している学科の事例を共有し、PROGテストをより有効に活用してもらう目的で開催されました。
はじめに、学長室(評価・IR担当)辻 由希部長が、毎年実施している自己点検評価や外部機関による認証評価を通じて、学習成果の把握と教育改善への活用が求められているとした上で、学生が卒業までに身につける「4つの力(自ら考える力・集い力・挑み力・成し遂げ力)」を測定するためにPROGテストを実施しているが、その結果を大学として、また学生自身がどのように役立てるかをこの研修をとおして考えていただきたい、と述べました。
続いて、株式会社リアセックの酒井 陽年氏から、内部質保証を実質化するための課題設定など、他大学における PROGテストの活用事例について報告がありました。酒井氏は、大学の内部質保証を進めるにあたり、まず各大学が目指すべき理想像を具体的に設定することが重要だと強調しました。例として、「大学生活満足度90%」や「対自己基礎力のレベル1の学生を10%減らす」といった、達成目標を明確にすることが挙げられます。その上で、設定した理想と、アセスメントテストやアンケートなどで把握した現状とのギャップを「課題」として捉え、このギャップを埋めるための具体的な施策を策定し、実行していくことが重要であると述べました。
後半は、国際学部国際学科 和田 龍太准教授が、専門ゼミナールでの取り組みを他学科の学生をモデルにデモンストレーションして紹介しました。まず、和田准教授が、独自で作成した自己分析シートを使い、学生自身が自分の長所と学生時代にやりたいことを洗い出して自己分析をさせ、その後、ペアワークで他者からみた自分を評価。さらには、PROGテストの結果から、それに影響した活動を考えさせて自己分析をしていく様子を再現しました。和田准教授は、「PROGテストは、1年次と3年次に受検すべき。伸びた項目に注目して学生自身が自分の強みをみいだし「ガクチカ(学生時代にもっとも力を入れたこと)」を把握することで、就職活動でのアピールがしやすくなる」と述べました。
最後に木村 英樹学長が、「卒業した学生には幸せになってほしい。そのために、日々の挑戦を大切にして大学生活を有意義なものにしてほしい」とチャレンジ精神の重要性を語り、「これからも東海大学の教育をよくするために皆さんと一緒に力をあわせていきたい」と結びました。
参加者からは、「(学生のPROGの)数値をただ見るのではなく、スコアがアップした点を『長所』として着目してあげるのは、学生の自己肯定感の向上につながると思うので、素晴らしいと思いました」「自分の長所と短所を把握し、短所に関しては克服するための対策や心がけを自分で考えた上で行動に移していきたい」などの感想が聞かれました。