
及川 留美 准教授
おいかわ るみ
所属 児童教育学部 児童教育学科
学位
修士(児童学)
研究分野
保育学
キーワード
#社会的子育て #保育実践 #子育てひろば #子育て支援 #保育者養成
みんなで子どもの育ちを支える社会の実現を目指して
親と子が共に育つ場「子育てひろば」の環境を考える
就園前の親子が過ごす場所として子育てひろばがあり、ここ20年ほどで急速に施設数が増加しています。孤立しがちな親子が交流したり、子育ての不安・悩みを相談したりできる場として子育て支援において重要な役割を果たしています。この子育てひろばは、支援の場としてだけではなく、親と子が共に育つ場としての機能も持っています。子育てひろばにおける環境(空間やモノの配置)が親と子の育ちにどのように影響するのかということについて研究をすすめています。

社会的子育ての実現のために
子育ては誰が行うものでしょうか。母親でしょうか、家族でしょうか。子どもを育てていくためには、本来たくさんの人の手を必要とします。家庭に閉じ込めてしまった子育てという営みを新たなネットワークで共に支えていくことを「社会的子育て」としています。この社会的子育ての実現のために、幼稚園や保育所などの保育施設で課題となっていることはなにか、社会的子育ての担い手を育てるために必要なことは何かなど、子育てを多角的な視点から検討しています。
地域への親しみを育む保育実践について
子どもたちが自分の住んでいる地域を好きになるきっかけは何でしょうか。幼稚園や保育園では、地域の人々との関りをなど通して、子どもたちが自分たちの住む地域に親しみを感じることが大切であるとされています。実際の保育現場での実践に触れながら、地域への親しみを育むための保育の工夫とその構造について調査・研究をしています。
及川先生が注力しているSDGs
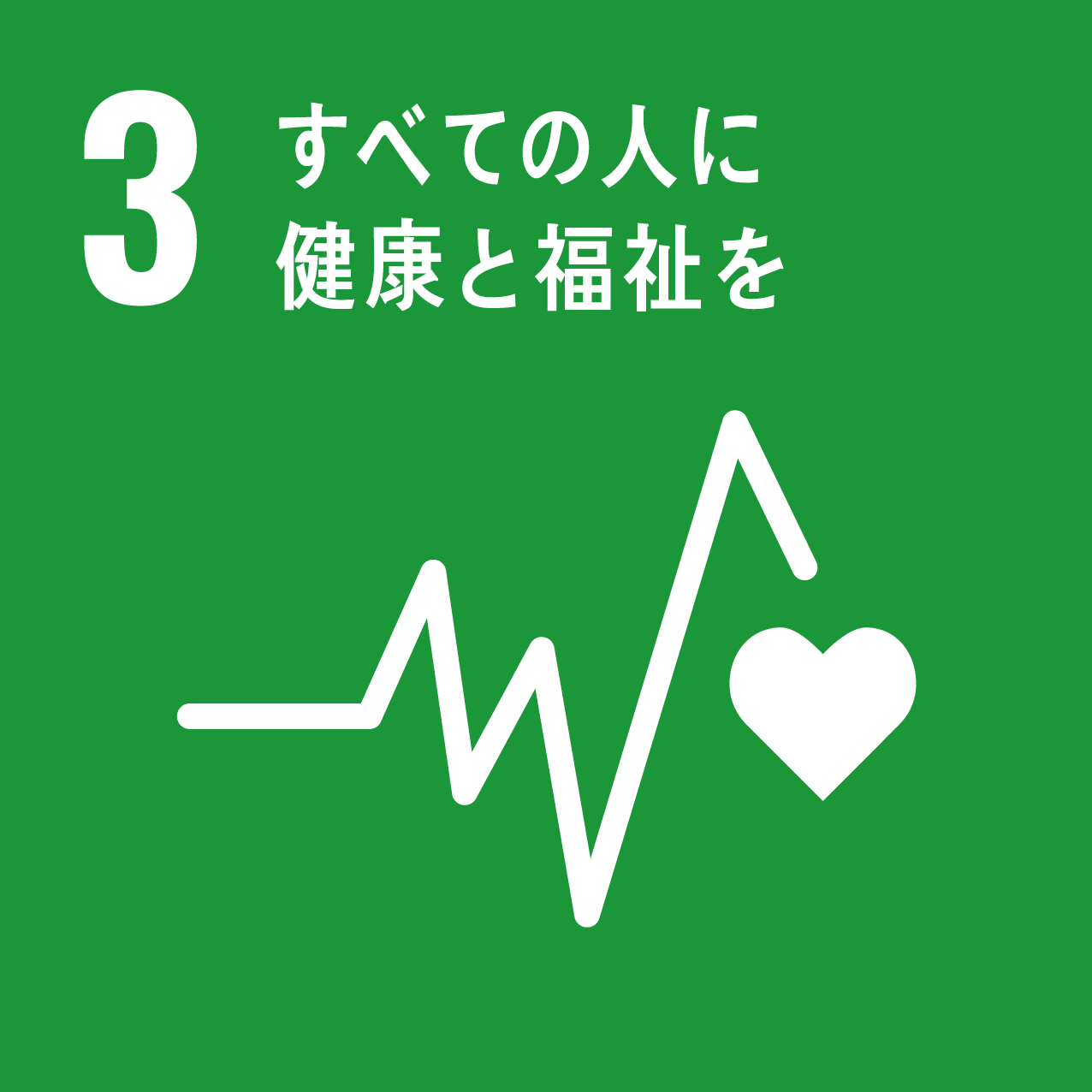
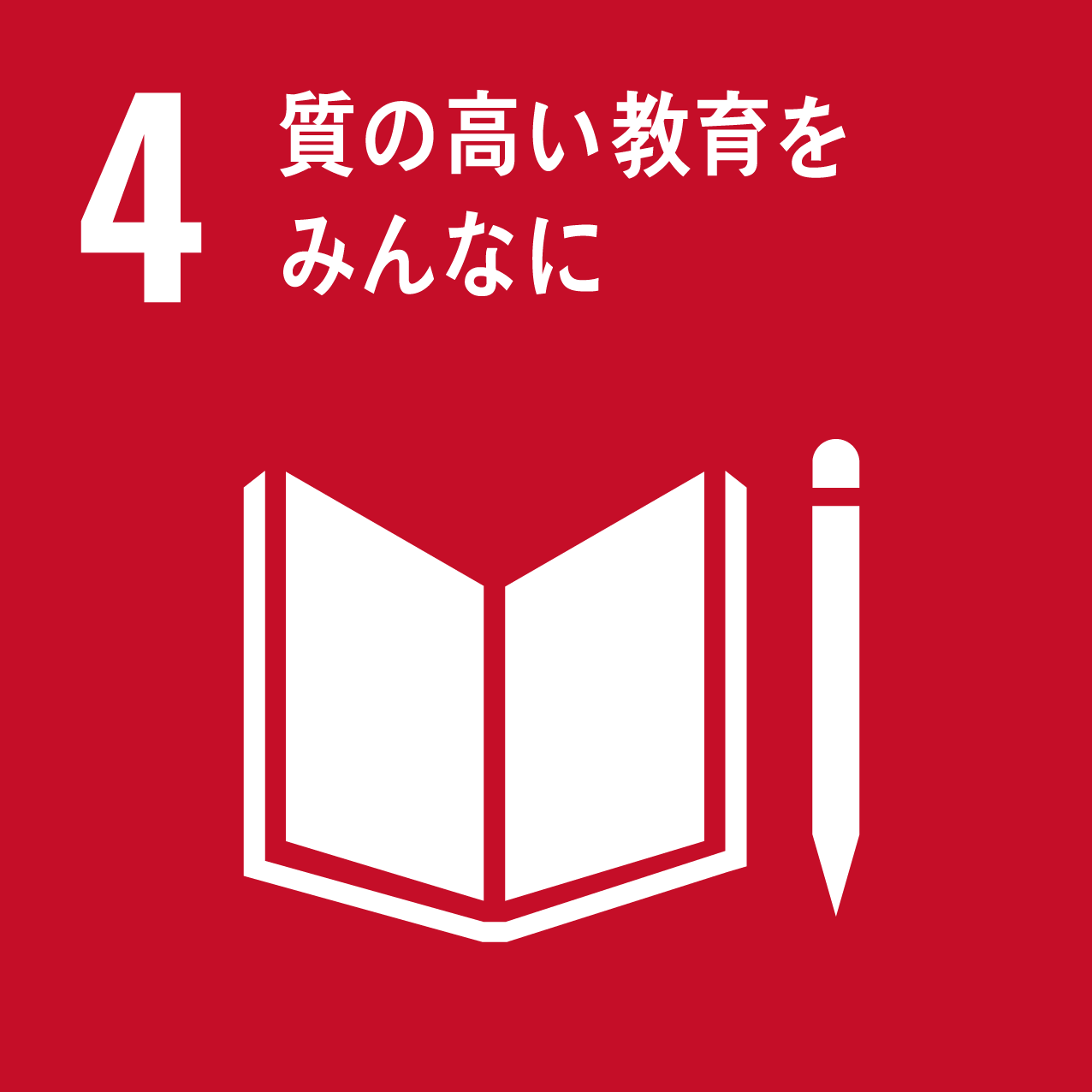

児童教育学科に興味がある受験生へ
子どもが尊重され健やかに育つ社会、子どもの成長に喜びを感じられる社会を作っていくためにはどうしたらよいのかという課題について、いろいろな視点から研究をしています。子どもの育ちの支え方はいろいろあると思います。これからの社会を担っていくみなさんも、ぜひ子どもの育ちを社会で支えていくことについて考えてみてください。
本研究内容に関心がある外部の方へ
子育て家庭への支援は、単なる経済的な支援だけではなく、子どもを安心して産み育てられる社会、子どもの成長を喜び合える社会を作ることが基本であると考えています。そのためには、子育てや子どもの育ちについて多角的な視点で検討することが重要です。






