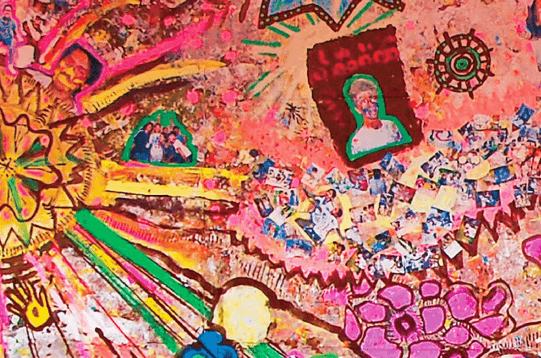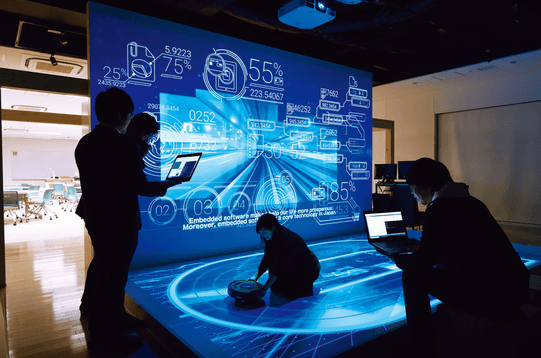政治経済学部経済学科の髙橋涼太朗特任講師が執筆した論文”Tale of a Missed Opportunity: Japan’s Delay in Implementing a Value-Added Tax”がこのほど、学術雑誌『Social Science History』(https://www.cambridge.org/core/journals/social-science-history)に掲載されました。
福祉国家を支える財源の一つである付加価値税(Value added tax, VAT)が日本で導入されたのは1989年のことでしたが、実際にはそれ以前から導入に向けた検討が進められていました。この論文では、このような動きがあったにもかかわらず、なぜ他の国々よりもVATの導入が遅れたのかという問いを明らかにするために、1960年代から1970年代の大蔵省主税局や税制調査会の議論を対象に歴史分析を行いました。
当時の日本でVATを導入するには、①直接税を基幹税に据えるというシャウプ勧告以後の直接税中心主義の転換、②増税の論理の生成、③VATが個別消費税よりも優れてるという根拠の生成という三つの論理が必要でした。この研究は、これらの論理が1960年代から1970年代にかけてどのように形成され、変化したのかを四つの時期に分けて追跡するものです。
第一に、1960年代の直接税中心主義とVATの劣位です。大蔵省主税局はシャウプ勧告やグードの著作の翻訳を通じて直接税中心主義を内面化しました。そのため、VATを含む間接税は劣位に置かれていたのです。加えて、個別消費税の方がVATを含む一般消費税よりも担税力を正確に測定できるという観点から優れていると評価されていました。すなわちVATの導入可能性は低かったと整理できます。
第二に、1968年の税収中立の生成です。大蔵省主計局は「財政硬直化対策キャンペーン」という財政規律の維持の圧力を大蔵省主税局に対してかけます。これを受けて、大蔵省主税局は所得税減税のための間接税増税、いわゆる税収を同じ規模にする税収中立策を採用しました。ここにおいて、直接税中心主義という論理は一部修正されます。しかし、依然として主税局は個別消費税が一般消費税よりも優れているという論理を採用していました。
第三に、1970年代初頭において、税制調査会基本問題小委員会が「高福祉高負担」を概念化し、ECへの海外調査研究に基づきVATの個別消費税に対する優越性の論理を確立しました。これにより、上述のVAT導入に向けた三つの論理が成立し、導入の可能性が高まりました。しかし、ニクソン・ショックとオイル・ショックの二つのショックによって「高福祉高負担」の概念は放棄されたため増税可能性は潰え、VATは導入されませんでした。
第四に、1970年代後半において、財政再建目的という観点からVAT導入がアジェンダ化しました。しかし、消費者、中小企業、与党内部からの強い反対に直面し、VAT導入の機運は潰えます。 最終的に、「財政再建に関する決議」が採択されます。これは、1980年代の一般消費税(仮称)による増税を排除するものであり「高福祉高負担」型の福祉国家への道を閉ざすことにつながりました。これらの複合的な結果として、日本が他国よりもVAT導入が遅れたことをこの研究は明らかにしています。